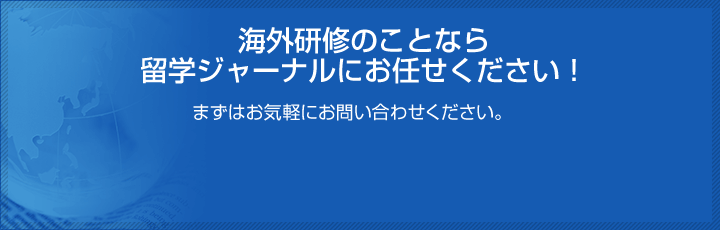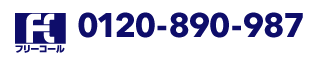学問として注目され始めた「アントレプレナーシップ(起業家精神)」
最近「アントレプレナーシップ(起業家精神)」が学問として注目され始めています。なぜ起業をあえて学ぶ必要があるのでしょうか。文部科学省の動きにも着目しながら、動きが加速する背景や、次世代のためにいま出来ることを探ります。
アントレプレナーシップが注目される理由とは?
アントレプレナーシップ(Entrepreneurship)とは、起業家精神と訳されます。会社を起こすための倫理、精神はもちろんのこと、組織論や資金調達に関する知識など、幅広い要素を含んで使われることが一般的です。
企業の創設に加え、社会におけるさまざまな問題を解決するための事業や、社内ベンチャーを立ちあげること、大学と企業が産学共同で新たな事業を始めたりすることも、起業の一種と言えるでしょう。つまり、目指すべき方向性やビジョンを持ち、自らの創意で新しく価値創造を事業として行うことがアントレプレナーシップだと解釈することができます。
日本では起業という言葉自体、まだ実感を伴いにくい言葉かもしれません。しかし、すでに多くの方がご存じのように、AIやITの発達により、10年~20年後には今ある仕事の約49%が無くなると言われています。これからは学校を無事卒業し、就職すれば安心、という時代ではありません。気候変動による影響など、予測不能なことも起きてくるでしょう。したがって環境の変化に対応し、自ら仕事を作り出す力が、自身にとっても社会にとっても、非常に重要になるというわけです。
文科省が推進する、次世代アントレプレナー育成事業(EDGE-NEXT)
では日本ではアントレプレナーシップをどのように身に付けられるかというと、最近までは学びやすいとは言えない環境でした。先進的な教育機関で特別プログラムとして開講されることはあったものの、機会が豊富とは言えず、一般的にはいったん社会に出てから大学院等で経営を学び、起業するのが主な流れでした。
しかしそれでは世の中の加速する動きに間に合いません。海外では20代、10代の若者が次々と起業しています。
国際調査結果においても、日本での起業活動は世界に比べ少ないものの、起業実現率(起業しやすさ)は決して低くない、という結果も出ています。かつては日本でも、パナソニックの松下幸之助が24歳、SONYの盛田昭夫は25歳で事業をスタートしており、若手が創業する勢いもあったはずです。
このような背景を受けて国も動き出し、文部科学省は2014年からグローバルアントレプレナー育成促進事業(EDGEプログラム)を発足させました。これは大学院生や若手研究者等を対象に、人材育成プログラムを開発・実施する大学等を支援するほか、イノベーション・エコシステムを構築して日本全体の取り組みを強化するものです。
現在はその第2ステージ、「次世代アントレプレナー育成事業(EDGE-NEXTプログラム)」に移行しており、前プログラムにより発生した教育課題を踏まえて、海外とも協力しながらより実践的なプログラムを支援しています。また経済産業省も、文科省と連動しながら起業家教育事業を行っています。つまり、国をあげてアントレプレナーシップ教育を推進させています。
2021年4月には武蔵野大学が学科としては日本初となる「アントレプレナーシップ学部」を創設します。進路選択の中に起業を想定した学部が入る、このような動きは他大学でも広がっていくのではないでしょうか。

次世代のイノベーションの担い手を育むために
それではもっと早い段階で、子供達の可能性を育み、イノベーターを増やすには何が必要かを考えてみましょう。
必要な素養としては、たとえば次のようなものが考えられます。
・思考の柔軟性をもつこと
・叶えたい夢を見つけること
・夢や目的を、他者に論理的に伝える力をつけること
・語学力を身に付けること
これらは日本でも学ぶことができますが、留学や、海外の人たちとの交流はとても有益です。なぜなら、特別な勉強をしなくても自然に身に付くからです。
個人的には、特に有効なのが「叶えたい夢を見つける」ことだと思います。当社はこれまで多くの高校生・大学生を海外留学に送り出してきましたが、「海外の友達が将来の夢を真剣に語っているのに驚いたし、刺激を受けた」という感想を多くいただいているからです。
留学先で「照れずに将来について友達と真面目に語り合え、いろんな意見を聞くことで自分のやりたいことが見つかった」「日本で友達との話題はタレントやSNSの話ばかりで、そうした体験がなかった」という人もいます。夢が見つかれば、それを叶えるために何かをしたいと、若者なら思い始めるでしょう。
加えて文化的背景が異なる人たちに自分の考えを伝えるためには、日本を外から見て柔軟に考える必要があり、また論理的に伝えるしかありません。また語学力は、言わずもがなでしょう。
留学はもちろん、国際交流で海外の人たちと触れ合うだけでも、多くの学びや気づきがあるはずです。これからの社会の変化に対応し、もし起業を志したら恐れずチャレンジできる人材育成のため、自身を見つめ、柔軟な発想を育める機会を提供していくことは、大切なことではないでしょうか。
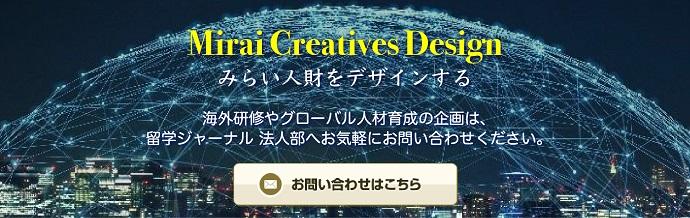
今回のコラム担当
法人部 媒体担当 A.M.
【Profile】
トビタテ!留学Japanサポーター。国家資格キャリアコンサルタント。新聞社、雑誌社、PR会社の勤務経験を経て現職へ。日本人の国際公務員を増やすべくWeb・雑誌で情報を発信するほか、媒体関連の企画立案等を行っている。
【中高・研修事例】留学2ヵ月前の事前準備講座を開催

留学は行くだけでも大きな学びがありますが、準備をすればするほど、より高い学びの効果が得られます。留学ジャーナルが行った「事前準備講座」をご紹介します。
【大学・実施例】シンガポール 語学研修+現地企業訪問

コロナ禍が明け、海外研修も本格的に再開した2023年8月に、留学ジャーナルでは大学にて「シンガポール 語学研修+現地企業訪問」(15日間)の研修を実施しました。あえてアジアで研修を行った目的や様子をご紹介します。
年代を問わない万能アクティビティ(研修)を行ってみる

「高いタワーを作ってみましょう」このひと言であなたはどのような行動が出来るでしょうか。そしてこの行動がどのようなに今後の人財育成に関わってくるのかをお話しします。