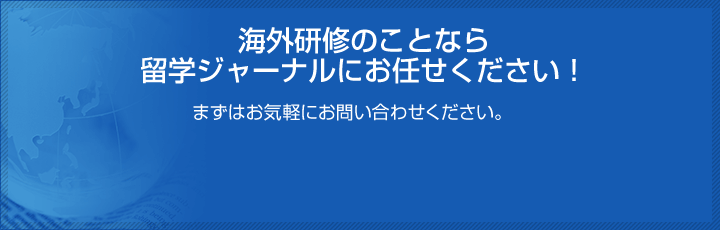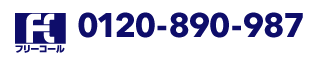今夏行われたオンライン国際理解教育プログラム~神奈川県立川崎北高等学校
この夏、神奈川県立川崎北高等学校様が、国際理解教育プログラム「Cultural Exchange Program with Australia」(3日間)を行いました。コロナ禍の海外留学に行けない期間に取り組んだ、オンラインによる初の取り組みは、どのようなものでしょうか。また成果は?
担当教師が寄せてくださった内容をご紹介します。
「Cultural Exchange Program with Australia」研修を行った理由と内容
<理由>
海外へ渡航し、国際的な視野を広げたり、異文化理解を図ったりする予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、実現が困難となったために行いました。
<内容>
・事前研修
・1日目:現地講師によるオンラインによるオーストラリアの基礎知識の学習、プレゼンテーションのコツなどの学習
・2日目:オンラインによる現地校生徒との交流(自己紹介、フリートーク)
・3日目:オンラインによる現地校生徒との交流(プレゼンテーション、フリートーク)
研修の成果・教員の感想
<成果>
・初めて海外にいる生徒と交流ができ、とても良い刺激となりました。
はじめはシャイでしたが、臆することなく英語を使ってコミュニケーションを取ろうとする姿勢が見られました。
・今後の英語学習へのモチベーション向上につながりました。
<教師の感想>
昨今の情勢にもかかわらず、このような貴重な経験ができたことは生徒自身の成功体験の獲得や英語力の向上につながりました。
また、今後の進路活動等にも大きく影響します。
国際理解教育プログラムの意義
<意義>
同じ年代の生徒同士でできたり、自校で実施できたり教員がサポートにつくことができるので、安心した環境で研修に臨むことができます。
<留学ジャーナルを利用して>
実施の3日間だけでなく、生徒の募集や事前研修などにおいても手厚くサポートをしていただき、大変感謝しております。
神奈川県立川崎北高等学校HP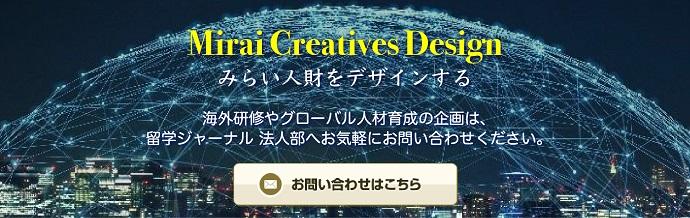
今回のコラム担当
R.H.
【Profile】
もともと渡航型の海外研修を検討され、国際教育に注力されるご予定だった高校様ですので、今回のオンラインを良いきっかけに、今後の海外研修企画に繋げていただきたいという思いで企画をしました。ご参加いただいた生徒の皆様もしっかりと海外の生徒と交流をし、外国人とコミュニケーションをとる良い機会が提供できたと感じております。 学校の国際教育への注力の良いきっかけとしてオンラインをご利用いただいた、とても良い事例となったのではないかと思います。
【中高・研修事例】留学2ヵ月前の事前準備講座を開催

留学は行くだけでも大きな学びがありますが、準備をすればするほど、より高い学びの効果が得られます。留学ジャーナルが行った「事前準備講座」をご紹介します。
【大学・実施例】シンガポール 語学研修+現地企業訪問

コロナ禍が明け、海外研修も本格的に再開した2023年8月に、留学ジャーナルでは大学にて「シンガポール 語学研修+現地企業訪問」(15日間)の研修を実施しました。あえてアジアで研修を行った目的や様子をご紹介します。
年代を問わない万能アクティビティ(研修)を行ってみる

「高いタワーを作ってみましょう」このひと言であなたはどのような行動が出来るでしょうか。そしてこの行動がどのようなに今後の人財育成に関わってくるのかをお話しします。