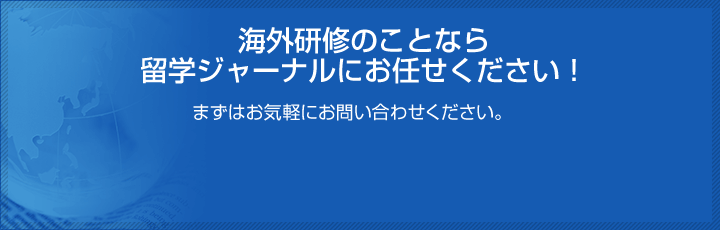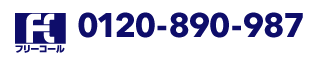セブ島「問題解決型学習(PBL)とインターンシップ研修」のご報告
 先日、フィリピンのセブ島で問題解決型学習(Project Based Learning=PBL)とインターンシップ研修を行い、お客様にとてもご満足いただきました。今回はそのご紹介です。
先日、フィリピンのセブ島で問題解決型学習(Project Based Learning=PBL)とインターンシップ研修を行い、お客様にとてもご満足いただきました。今回はそのご紹介です。
日本では「"Teaching"が主で、先生が生徒に教科書を使って教室で教える」という教育をしている学校が多いですが、海外では「生徒に自主的に考えさせる」という教育方針を取っている学校が多いのです。このような背景から、近年は日本でも、文部科学省がすすめるアクティブラーニングの教育方法として「問題解決型学習(以下PBL)」が非常に注目されています。アクティブラーニングの目指すところは「正解・解答のある課題に取り組み、知識・技能を得ること」ではなく『正解のない議論(課題)を通して、問題解決へのアプローチ方法を身につけること』です。最終的に「主体性・協働的に問題を発見し、解決する能力」を養うことを目的としています。
実際にはPBLでは以下の6つのステップを踏んでいきます。
① 問題に出会う(テーマを決める)
② どうしたら解決できるのか実践的・論理的学法によって考える(解決策を考える)
③ 相互に話し合い、何を調べるのかを明確にする
④ 自主的に学習する
⑤ 新たに獲得した知識を問題に適用する
⑥ 学習したことを要約する
問題の答えを出すことが目的ではなく、この「答えにたどり着くまので過程(プロセス)自体が重要」である、というのがPBLの学習理論です。PBLの教育方法には2種類あり、まずは、1つの課題に対して仮説を立て、6つのステップに沿って検証していく「チュートリアル型」。そして、課題を日社会の中に設定し、民間の企業など実社会に入り込みながら6つのステップを踏んで問題を検証していく「実践体験型」があります。
先日、セブ島で行った大学生向けのPBLは「実践体験型」を実施しました。
セブ島にある、オーガニックの化粧品などを取り扱っている会社の経営者に会い、この会社の問題解決してほしい案件を伺い、ショッピングモールでセブに住んでいる人に要望や現状をヒアリングして、"消費者は何を望んでいるのか"をまとめて経営者に提案しました。参加者の大学生のみなさんからは「消費者と経営者が望んでいることの"違い"が売り上げにつながっていない、という問題を発見でき、とても有意義だった」と発表がありました。経営者の方々からは「経営の立場からだと見えない部分を知ることができ、今後の売り上げ拡大につながる」と感謝の言葉をいただきました。また、このような学習をすることで、問題解決方法の手順がわかるばかりでなく、フィリピンと日本の違いも実感することができたという声もありました。
 PBLが終わった後は、カフェでのインターンシップも行いました。日本の大学生のみなさんは「フィリピンではカフェ文化があまりないのでは?」と思っていたようでしたが、カフェ文化は世界共通なんだということに気がついたり、同じコーヒーを飲むにしても、フィリピンでは甘いものが好まれるなど、現地の嗜好についても学ぶことができたようです。
PBLが終わった後は、カフェでのインターンシップも行いました。日本の大学生のみなさんは「フィリピンではカフェ文化があまりないのでは?」と思っていたようでしたが、カフェ文化は世界共通なんだということに気がついたり、同じコーヒーを飲むにしても、フィリピンでは甘いものが好まれるなど、現地の嗜好についても学ぶことができたようです。
研修期間としては、10日間という期間でしたが、参加してくれた大学生からは「日本でインターンシップするよりも、有意義かつ日本を客観的に見る機会となり、自分自身が日本でどのようなことがやりたいか、がわかった」という声もありました。
留学ジャーナルではこのような研修も企画・手配が可能です。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
今回のコラム担当
大阪支店 Y.K.
【Profile】
学生時代に学校の研修ツアーでカナダへ行き、初めて海外のすばらしさに出会う。 電車で寝てる人がいないこと、自分の夢を語る人が多いことに感動し、卒業後に長期留学を決意!したものの…親に反対され、就職。社会人になってから自分でお金を貯めてアメリカ・カリフォルニアのサンタバ―バラに留学。その際、留学で困っている人とたくさん出会い、帰国後は「 留学関連で仕事をしたい」と思い現在の仕事に至る。
【中高・研修事例】留学2ヵ月前の事前準備講座を開催

留学は行くだけでも大きな学びがありますが、準備をすればするほど、より高い学びの効果が得られます。留学ジャーナルが行った「事前準備講座」をご紹介します。
【大学・実施例】シンガポール 語学研修+現地企業訪問

コロナ禍が明け、海外研修も本格的に再開した2023年8月に、留学ジャーナルでは大学にて「シンガポール 語学研修+現地企業訪問」(15日間)の研修を実施しました。あえてアジアで研修を行った目的や様子をご紹介します。
年代を問わない万能アクティビティ(研修)を行ってみる

「高いタワーを作ってみましょう」このひと言であなたはどのような行動が出来るでしょうか。そしてこの行動がどのようなに今後の人財育成に関わってくるのかをお話しします。