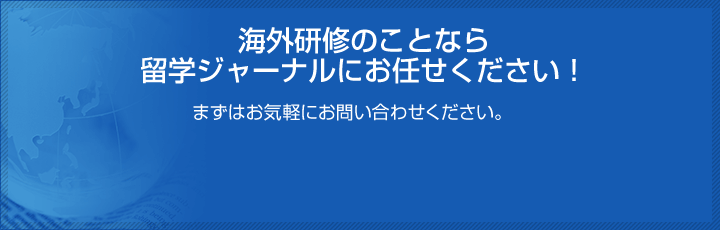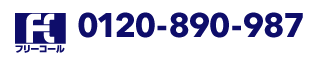アメリカの車事情について
私はアメリカ留学中に車を運転していました。アメリカで運転免許を取得し、自分で車を購入し、メンテナンスまで行っていましたが、日本の車社会と比べて非常に違うので、非常に多くのカルチャーショックを受けました。今回は私が留学中に驚いた、アメリカの車事情について共有させていただきます。
運転免許証の取得までの流れ
私が留学していたワシントン州では国際免許は有効期限が3ヵ月と決まっているため、それ以上車を運転するためには、現地で運転免許証を取得する必要がありました。私は既に日本の運転免許証を取得していたため、日本で勉強する講義などはありませんでしたが、学科試験と実技試験がありました。学科試験に関しては、日本語で受けることが可能でしたが、アメリカの交通ルールを事前に勉強しておく必要はあります。 また、皆さんご存知のようにアメリカは右車線の車両は左ハンドルですし、実技試験では英語で指示をされるのに加え、日本との交通ルールの違いなど、多くの事に戸惑いました。ただ、指示通りに正しく運転すれば、特に難しいことはないと思います。
また、皆さんご存知のようにアメリカは右車線の車両は左ハンドルですし、実技試験では英語で指示をされるのに加え、日本との交通ルールの違いなど、多くの事に戸惑いました。ただ、指示通りに正しく運転すれば、特に難しいことはないと思います。日本のように、何回も学科試験を受講し、複数回の路上教習もすることなく、私は一回の試験で合格し、無事にアメリカの運転免許証を取得することができました。また、免許証を取得するためにかかった費用は、日本では約30万円かかるのに比べ、アメリカでは約2万円と安価で取得できます。アメリカで免許証を取得すると身分証明書の代わりにもなるので、機会があれば免許取得に挑戦してみてください。
車の購入の仕方
車の購入の仕方も日本と大きく違います。購入方法は大きく分けて2つあります。1つ目は、ディーラーから車を購入する方法です。メリットとしては、車両点検など難しい手続きはすべて代行してくれます。車の購入手続きに不安な方や、整備不良がある車は購入したくないという方は、ディーラーから購入することをおすすめします。2つ目は個人から購入する方法です。私はこの個人売買という方法で車を購入しました。個人売買では、さまざまなサイトから売り手を探し、直接連絡を取って取引をします。ただ、日本人であれば安心ですが、日本語が通じない場合ですとトラブルが起きたり、整備不良の車を買わされてしまう可能性もあります。でも、直接値切り交渉ができたりすることもあるので、ディーラーから購入するよりかは、安価で車が購入できます。そのため、個人から車を購入する際は、整備不良などがないか、事前に点検してもらうことをおすすめします。私は50万円くらいで車を購入しましたが、事前に車両点検をしてもらったので、すぐに故障したりというトラブルは特にありませんでした。
交通ルールについて
右車線を運転するほかに、アメリカには独自の交通ルールがあります。その中でも特に私が驚いたルールが、「赤信号でも右折ができる」というものです。もちろん日本では、赤信号の場合、直進も右左折も禁止ですが、アメリカの場合だと、赤信号でも進行方向からくる車や、歩行者がいなければ右折ができます。これは、アメリカの車社会ならではの渋滞緩和などの防止策のためと言われています。 そのほか、進行方向に関係なく、一時停止した順に一番早い車が優先される「ALL WAY STOP」や、対向車線でもスクールバスが走ってきたら、車を停止しなければいけないルールなどさまざまです。また日本では、停車する際や、道を譲ってもらった際に感謝の意味を込めてハザードランプを点滅させますが、アメリカの場合、ハザードランプを点滅させると、それは「エマージェンシー」つまり緊急事態を知らせる合図になってしまいます。
そのほか、進行方向に関係なく、一時停止した順に一番早い車が優先される「ALL WAY STOP」や、対向車線でもスクールバスが走ってきたら、車を停止しなければいけないルールなどさまざまです。また日本では、停車する際や、道を譲ってもらった際に感謝の意味を込めてハザードランプを点滅させますが、アメリカの場合、ハザードランプを点滅させると、それは「エマージェンシー」つまり緊急事態を知らせる合図になってしまいます。さらに、アメリカの高速道路は日本と違い、無料で走行できる道路が数多くあります。一部有料道路もありますが、私が運転していたワシントン州では、無料で走行できる高速道路が多かったので、ドライブに行く際でも気軽に運転して遠出することができるのも魅力です。
みなさん、いかがでしたでしょうか。アメリカの車事情について、日本との違いを簡単に述べさせていただきましたが、もちろん車を購入しなくても、バスや電車といった公共交通機関を利用すれば不便はしません。アメリカは日本のように車検というものがありませんので、道路にはお洒落に塗装された車や、カスタマイズされた車も多く見受けられます。是非、アメリカに行った際には、日本と違った車文化に触れてみてくださいね!
今回のコラム担当
法人部 K
【Profile】
大学四年を休学してアメリカ・シアトルへ長期留学。現地のコミュニティカレッジではビジネスを専攻する。留学中には学生団体の発足やボストンキャリアフォーラムへの参加など幅広く活動。また日系留学エージェント会社でインターンシップを経験。現在は自身の留学経験を活かし、主に大学や英会話学校などに出向き留学相談に従事している。
【中高・研修事例】留学2ヵ月前の事前準備講座を開催

留学は行くだけでも大きな学びがありますが、準備をすればするほど、より高い学びの効果が得られます。留学ジャーナルが行った「事前準備講座」をご紹介します。
【大学・実施例】シンガポール 語学研修+現地企業訪問

コロナ禍が明け、海外研修も本格的に再開した2023年8月に、留学ジャーナルでは大学にて「シンガポール 語学研修+現地企業訪問」(15日間)の研修を実施しました。あえてアジアで研修を行った目的や様子をご紹介します。
年代を問わない万能アクティビティ(研修)を行ってみる

「高いタワーを作ってみましょう」このひと言であなたはどのような行動が出来るでしょうか。そしてこの行動がどのようなに今後の人財育成に関わってくるのかをお話しします。