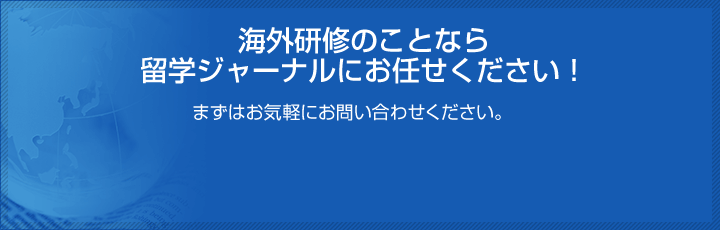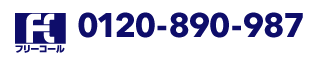2016.03.06 「ぐんま国際アカデミー(GKA)ドキュメンタリー映画祭」開催
 過日、ぐんま国際アカデミー(GKA)10年生(高校1年)による映画祭が開催されました。
過日、ぐんま国際アカデミー(GKA)10年生(高校1年)による映画祭が開催されました。
同校はインタビューページにもあるように、国際バカロレア(IB)校としての認定を受け、国際人を育成する理念を掲げた学校です。校内は英語環境が整っており、校内放送や「土足禁止」のサインなどもすべて英語・日本語両方で、バイリンガル教育を徹底しています。
映像に関しては、まず10年生は1年間をかけて、映像制作を基礎から学び、10~15分の映画を制作。その集大成として今年、第1回目となる映画祭を開催。プロジェクトの顧問でもある諏訪敦彦監督と、タレント/女優のサヘル・ローズさんらゲストを招き、優秀賞を決定しました。
映画制作教育の狙いは、全人教育×グローバル人材の輩出
 映画制作プロジェクトを担当する小田浩之先生によると「この教育の狙いは、映像をツールとした全人教育です。
映画制作プロジェクトを担当する小田浩之先生によると「この教育の狙いは、映像をツールとした全人教育です。
映像制作にはクリエイティビティ、チームワーク、リーダーシップ、コミュニケーション力など、さまざまな教育的要素が関わります。題材は日本や地域の異文化共生、産業等の特色・魅力等。英語字幕またはナレーションを付けることにより、日本を世界に発信できるようにします。
このアクティブラーニングを通して、グローバル人材に必要な能力資質を高め、国際的な支店で地域の課題を考えることのできる人材を輩出することを目的としています」とのこと。
映画祭出品作品のテーマ
 上映された作品は全7作。
上映された作品は全7作。
テーマは「お化け」「落語」「干し芋」「ハロウィーン」「祭り」…など。どれも押しつけられたものはなく、生徒たちが自ら選びだしたテーマと内容です。
いくつかの作品の中には、留学ジャーナルが企画した海外研修先である、映画学で名高い南カリフォルニア大学の講師や、サンディエゴの高校生とのディスカッション映像を効果的に使った作品もありました。留学体験は、高校生に何かしらの印象や影響を与えたことがうかがわれます。
ふだんから英語に触れている学生たちは、現地の生徒らと実際に意見を交わすことにより、より深く日本と海外の違いや自分たちの住む環境などについて考え始めた様子です。
最優秀作は『湯煙タトゥー~あらわになりはじめた文化同士の衝突~』
 最優秀賞を受賞したのは、有力な観光資源である温泉で、タトゥーをいれた外国人が入浴できない問題。
最優秀賞を受賞したのは、有力な観光資源である温泉で、タトゥーをいれた外国人が入浴できない問題。
日本では昔からタトゥーが“反社会的”と見なされてきた反面、海外ではファッションや生き方のひとつとして受け入れられているという違いをインタビューを通して浮き彫りにしただけでなく、さらに「問題は日本国内にもあった」とし、無理に解決するのではなく、もうひとつの問題をあえて提起した作品です。
受賞した生徒たちに、作品と留学の関係について聞いてみました。
「留学したことで、外国人に分け隔てなく接することができるようになりました。海外の人の考え方を持って帰れたので、留学体験は生きたと思います」
「英語のインタビューも自分たちでやりました」
「日本人が考えているタトゥーの考え方と外国人の考え方が、まったく真逆だったのでびっくりしたし、今後の考え方にもつながるかな、と思いました」
今回は答えが出せなかったので、時間があれば同じメンバーで最後まで考えたい、と言う彼女たちの考える力、考えようとする力に、真の全人教育と、留学が及ぼす影響力について改めて認識させられた1日でした。
今回のコラム担当
留学ジャーナル編集長 M
【Profile】
新聞社、TV局、雑誌社、PR会社等を経て現職へ。留学情報を媒体を通じてお伝えするのはもちろん、近年では日本人による国際公務員の応募を増やすべく、雑誌とWebで連載も掲載中。 国家資格キャリアコンサルタント トビタテ!留学Japanサポーター
【中学生】マレーシア サマーキャンプで生徒達は何を学んだか

中学生を対象に、留学ジャーナル主催の「名門インターナショナルスクールでサマーキャンプ&SDGsを学ぶinマレーシア」が催行されました。 10日間の海外スタディツアーで、生徒たちが体験し、学んだことをレポートします。
【中高・研修事例】留学2ヵ月前の事前準備講座を開催

留学は行くだけでも大きな学びがありますが、準備をすればするほど、より高い学びの効果が得られます。留学ジャーナルが行った「事前準備講座」をご紹介します。
【大学・実施例】シンガポール 語学研修+現地企業訪問

コロナ禍が明け、海外研修も本格的に再開した2023年8月に、留学ジャーナルでは大学にて「シンガポール 語学研修+現地企業訪問」(15日間)の研修を実施しました。あえてアジアで研修を行った目的や様子をご紹介します。