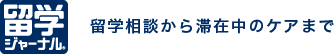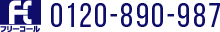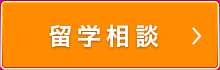| オフィス到着、メールチェック | |
| UNVバンコク事務所とスカイプ会議。ほかの国連機関とのジェンダーをターゲットにしたジョイントプログラムについての打ち合わせ | |
| 本部内でミーティング | |
| 会議用レポートの追い込み | |
| 同僚たちとランチ。国連内のカフェか近隣の社食に食べに行くことが多い | |
| UNVパナマ事務所とスカイプ会議。HIVエイズプログラムの書類作成について討議 | |
| ほかのプログラムやコンセプトノートへのジェンダー分析を行う。新たに作成されたポリシーにジェンダーの視点が反映されているかをチェック | |
| 同僚とともに帰宅 |

グローバルに社会貢献ができる国際機関で働くには、どのようなステップが必要なのだろう。
いま活躍する日本人職員に、その道のりを聞いた


女性の地位を向上させるため国連のプログラムにかかわる
肩書きはジェンダー分析官(アナリスト)。国連開発計画(UNDP)の下部組織、国際ボランティア計画(UNV)で、女性の地位を向上させるための分析やアドバイスを行う石井はるかさんはこう話す。
「女性を力づける(エンパワーする)職務ですが、私自身、国連の仕事を通じてエンパワーされたひとりです」
国際ボランティア計画の本部、ドイツのボンで、昨年から現職に就いている。国連ボランティア計画が推進する、環境問題や平和構築などに関するプログラムに「男女平等の視点」が反映されているか、分析や評価をし、必要があればアドバイスもする。
「国連が手がけているプログラムに、女性のニーズは反映されている? 参加率は? 女性はリーダーシップを取っている?といった、ジェンダー平等の視点を盛り込んでいきます」
国連はいま、女性の地位向上を重要課題のひとつにしている。ところが、現状ではまだ女性のニーズに特化したプログラムは多くない。加えて、女性職員が多い国連でさえ、トップレベルのリーダーとなるとまだ少数だ。石井さんはこうした課題に一つひとつ向き合い、女性の地位を向上させるために何ができるのかを考えるのが仕事だ。
2002年4月早稲田大学社会科学部入学
2007年8月米国ニュースクール大学大学院入学「国際
情勢学・人権」専攻
2008年6月香港の人権NGOにて、ネパールにおける
拷問の問題およびカーストに基づく差別の
問題に携わる
2008年9月国連人口基金NY本部で学生コンサルタント
としてジェンダーに基づく暴力プログラム
に従事
2009年1月国連女性開発基金NY本部で
学生コンサルタントとして女性、平和安全保障に
関する国連安保理決議等に従事
2009年6月国連経済社会理事会NY本部・障害者
権利条約事務局にてインターンシップ
2009年9月国連人権高等弁務官事務所ジュネーブ本部・
女性差別撤廃条約事務総局にて
インターンシップ
2011年6月 国連開発計画カンボジア
国連開発計画カンボジア
事務所にてジェンダー
に基づくGBV専門官として勤務
2014年3月JPOとして国連ボランティア計画ボン本部
にてジェンダー分析官として勤務開始
同じ女性の境遇の違いに
カンボジアで衝撃を受けた
ジェンダーの問題に深くかかわるようになったきっかけは、カンボジアでのフィールドワークだった。
「カンボジアで同世代の女性に出会ったのですが、彼女は人身売買の被害者で、背景には貧困問題があった。たまたま私は東京、彼女はカンボジアで生まれたけれど、場所が違えば私が彼女の立場だったかもしれない。私は日本で問題意識もなく生きていていいのか。何か行動をしなければと強く思いました」
大学院を卒業後の2011年、広島平和構築人材育成事業の研修生として、UNDPカンボジア事務所に駐在した。国連開発計画という組織で、GBV(性にまつわる暴力)の専門官として、政府やNGO、地元のボランティアスタッフとともに問題解決に取り組んだ。
海外留学を志したときはまだ、自分の進む道ははっきりしていなかったが、外国語が堪能だった祖父の勧めがきっかけになった。
「英語でコミュニケーションできれば出会う人の数が増える。夢は何でもいいけれど、語学をツールに世界を見ないといけない」
アメリカでの留学当初は言葉がよくわからず、右往左往の連続だった。
「キャンパスで学生IDをつくるのに事務のスタッフと英語が通じず8時間かかって泣く泣く帰りました」
英語を質問できる友だちをつくり、毎クラス後、先生にわからないところを聞きにいき、必死にくらいついた留学時代。「どんな環境でも切り拓くことができる」という自信が後にインターンや仕事で滞在した香港、ジュネーヴ、カンボジアでの経験にいきた。
カンボジアでは家庭内暴力や人身売買など、問題に直面した女性たちが、どのようにしたら第三者に助けをもとめやすいシステムができるのかを考え、都市部のみならず、地方にも頻繁に足を運んで「ワンストップ」(一連の手続きが一度にできる)のサービスを提供するシステム作りに貢献した。
「自分が少しでも世の中に貢献できることがある。この思いが私のエンパワーメントになり、国連で働いていく動機になりました」
人間はみな平等、の理念のもとボランティアと力を合わせる
3年間勤務したフィールドを離れ、14年から本部に勤務したのは、「ジェンダーの問題を法的観点や経済的自立など、もう少し大きな視点で考えたかったから」と話す。
国連には紛争を逃れ、難民だった職員などもいる。強い使命感を持つ同僚たちに圧倒されたこともあるが、今は自分として、日本人として「自分のものさし」に自信を持てるようになった。
「例えば私の母は相手が社長でも、ホームレスの方でも一緒に同じように話をする。人間はみな対等というのは人権の基本的な考え方ですよね。もし、ほかの人と同じ権利が享受できない人がいるならば、何かしなければいけないと思う。この気持ちはみな一緒。国連で働けば問題に関われる機会が多くなる」
いつも心を揺さぶられるのは、各国で働くボランティアスタッフの存在だ。自分たちの生活が豊かではなくとも、このような活動に身を捧げる人も多い。「この問題を解決したい」という強い決意で携わっている。
ボランティアのためにも、世界の人々のためにも、ボランティアの活動や取り組みを伝えることが重要と感じている。
「問題に向き合う姿勢やコミットメント(かかわり)の度合いがとても強く、刺激を受けます。このような人たちに出会えたのが国連で働く喜びなのです」
自分の力で成し遂げる
ことが大きな自信に
留学するまでは海外生活の経験がなく、学校の授業がわからないことも多かった。「質問できる友だちを見つけ、先生には毎回の授業後にわからないところを聞きにいった」という石井さん。
業務ではひとりで現地事務所に派遣されることもあるが、留学時代に自分の力で状況を切り拓いた経験が大きな自信になっている
大量に読み書きする
スピード感をつける
大学院に留学時代は、課題として次のクラスまでに3冊本を読まなければいけなかったり、論文を作成したりと、大量に英文を読んで、書く力がついた。
「国連でも大量のリポートを読み込み、資料を作る。留学時代は大変だったが、スピード感が身につき、今の仕事に役に立っている」という。現在はフランス語など多言語に挑戦中だ
自分のものさしをつくり
他者との違いを楽しむ
「日本では自己主張しすぎて、生意気に思われてしまうかもしれません」という石井さん。留学時代に自分がどう考えるかを伝えなければいけない機会が多かったため、自分の視点が養われた。国連はさまざまな地域から職員が集まっているので、背景や「ものさし」も違うのがあたり前。「困難と思わず、違いを楽しんでいます」
国際ボランティア計画(UNV)の活動
 UNVとはUnited Nations Volunteersの略で、1970年に創設。
UNVとはUnited Nations Volunteersの略で、1970年に創設。
開発途上国における開発支援や、紛争地域での緊急援助、その後必要とされる平和構築活動などに貢献する意志のある人々を募り、各国の国連機関の要請に応じてボランティアとして現地に派遣する。協力には実務経験のある「国連ボランティア」、若手による「国連ユース・ボランティア」、オンラインでボランティア活動ができる「オンライン・ボランティア」がある。年間約7,000人が世界約130ヵ国で任務を遂行している。





国際公務員になるためのキーワード!
国連ボランティア(UNV)に採用されると国際機関のフィールドに派遣され、開発支援や人道援助の活動に実際に従事できるため、将来、国際機関の正規職員を目指す人が職務経験をする手段として非常に有効だ。応募条件は25歳以上、大学卒、2~3年の専門分野での勤務経験等となっている。勤務期間は通常1年~2年。UNVは俸給はなく、現地で必要な生活費が支給される。その額は月およそUS$1,200~2,000。応募はオンラインでの登録のみ。UNV本部サイトにアクセスの上、必要事項を記入(英文)後、送信する。 UNVは開発分野、緊急人道支援、平和構築や選挙支援・民主主義の推進、人権擁護、自動車整備、航空管制、通信など100種類以上の職種にわたる活動を行なっている。