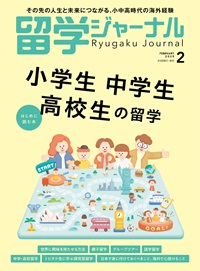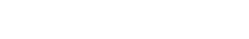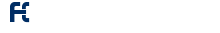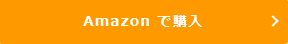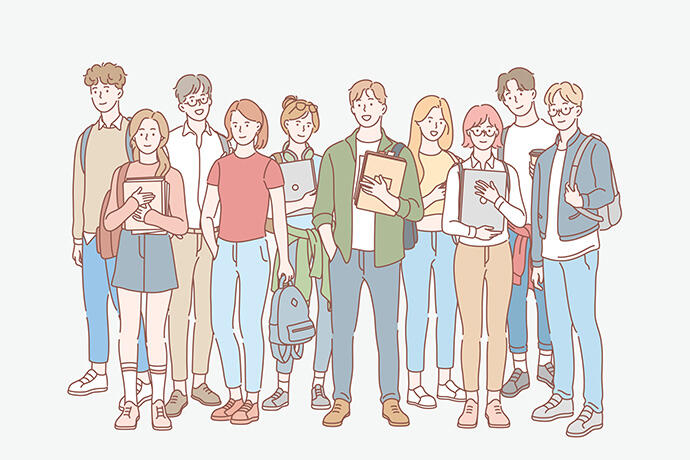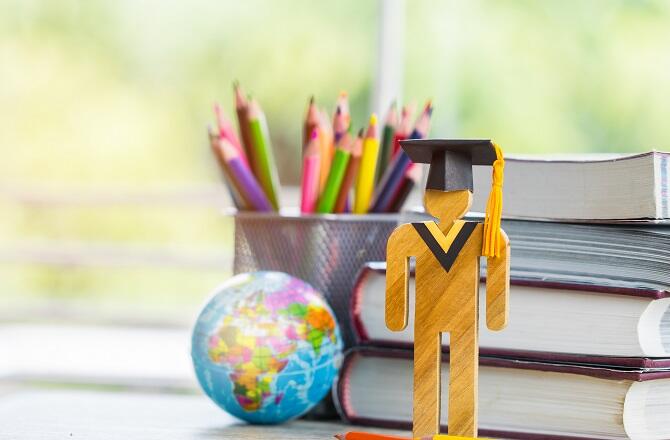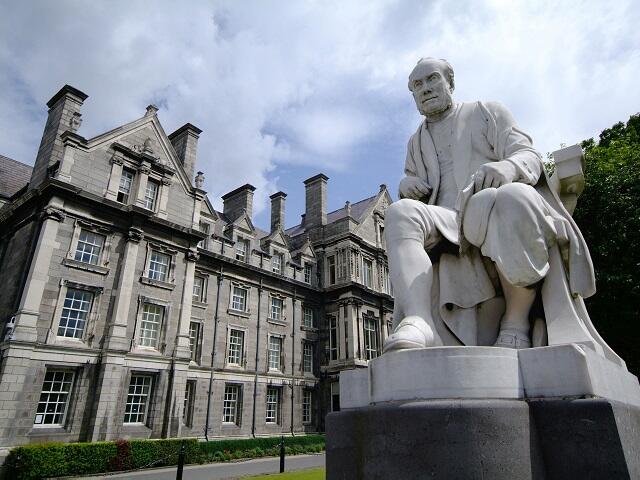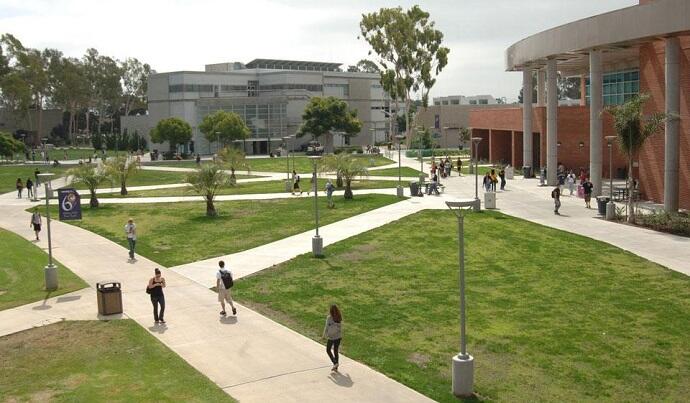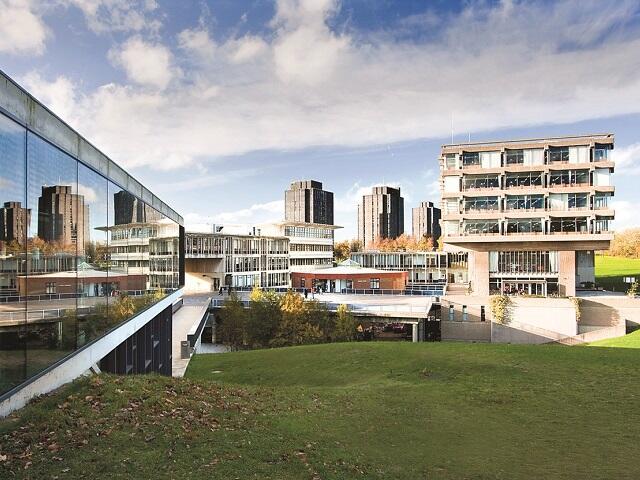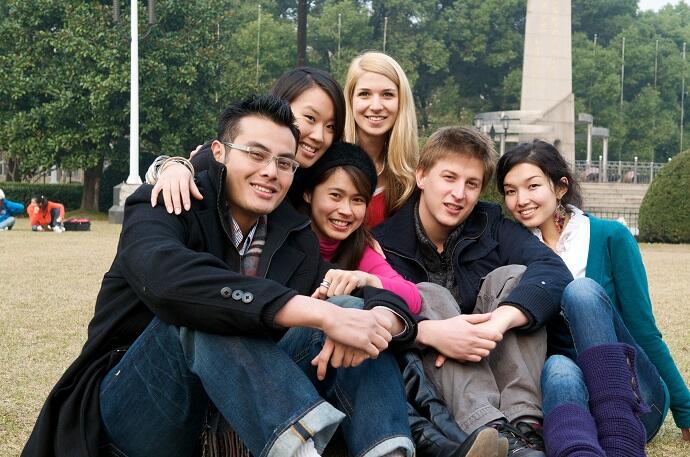「グローバル人材に育ってほしい」「世界を知ってほしい」。親がそう願っていても、子どものやる気が伴わないと、なかなか実現は難しいもの。子どもの興味・関心を海外に向けさせるには?その必要性は?
高校で国際教育に携わる建元喜寿さんにお聞きしました。
世界に無関心なまま生きられる時代ではない

教えてくれたのは…
筑波大学附属坂戸高等学校 主幹教諭
建元喜寿さん
農業科担当。筑波大学附属学校国際教育推進委員も務める。持続可能な開発のための教育(ESD)の視点に立った、国際協働プログラムの開発などを担当している。
私は農学と環境科学を専門にしています。農業の面から見ても、日本国内で営みを完結することはできません。野菜の種子の自給率は1割以下、残り9割は外国から輸入していると言われています。技能実習生を受け入れている生産現場もあります。そうして生産された物が皆さんの食卓に並び、生活を支えているのです。
視線を街に移すと、特に都市部や観光地を歩けば、たくさんの外国人の方を目にします。旅行している方もいれば、店舗で働いている方もいますよね。こうした社会を生きていくために、世界に目を向けることは現代の子どもたちにとって必須の経験になっていると言えます。
併せて、当事者性とコミュニケーション力を伸ばすことも大切だと考えています。当事者性のある人とは、他人任せにせず自ら社会の出来事に関心を持って考えられる人のことです。もう一方のコミュニケーション力は、意思疎通に必要なスキル全般を指します。料理が得意だからジェスチャーを交えて一緒に料理をしてみる、など言葉だけに頼らない距離の縮め方もスキルのうちです。
しかしこうした力は実感が伴わないとなかなか伸ばせません。そこで必要なのがさまざまな人と接し、世界とのつながりを発見する体験です。自分に関係のあることなんだ、と子どもに思ってもらいやすくなります。
小中高時代に育みたいチカラ
これからの時代を生きるため、高校卒業までに特に身に付けたいのが以下の2つの力。
コミュニケーション力
社会に自分なりの切り口で関わり、日本人、外国人を問わず、文化的背景が異なる人たちとお互い理解し合うために、コミュニケーション力は欠かせません。日本語以外の語学力は当然あった方がいいですが、他に、話題を見つける力、筋道立てて考える力、表情や態度といった非言語能力も大事になります。子どもたちそれぞれが得意な部分を見つけられるといいですね。
当事者性
グローバル社会だと言われても、子どもたちはどこか遠い存在に感じたり、英語が得意な人だけに関係のあることだと思ったりしてしまいます。しかし、誰にとっても他人事ではありません。子どもたちが口にする食材も、接している情報も、街で出会う人々も国を越えて行き交っています。そうした社会で生きているという意識を持つことがまず大切だと私は考えています。
いま政治・経済・社会などあらゆる分野で、ヒト・モノ・カネ・情報が国や地域の枠組みを越えて移動しています。そんな世界的な競争と共生が進む時代に対応できる力を持つ人、それがグローバル人材です。必要な要素として以下のようなものが挙げられています。
要素1:語学力、コミュニケーション能力
要素2:主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感
要素3:異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー
「グローバル人材育成戦略」(グローバル人材育成推進会議、2012年)より
2つの経験がその後の基盤に
当事者性とコミュニケーション力の成長を助けるのは、ちょっとした体験の積み重ねになります。特に、以下の2つの経験はその後の人生の基盤になります。
多種多様な人との出会い

私は子どもたちに未知のヒト・モノ・コトに対して壁をつくらないでほしいと思っています。そうなるには慣れが必要です。
まずは多様なバックグラウンドを持つ人と直接関われる機会が、日常的にあるといいですね。そして、新しいことを知る楽しさを体感してほしいです。相手と仲良くなり、興味を持って接するようになると“伝えたい”という欲求も芽生えるでしょう。
身近な「世界とのつながり」探し

将来、日本で暮らすにしても、海外で暮らすにしても、世界とのつながりは断ち切れません。しかし、そう説明しても子どもたちはピンとこないでしょう。
そこで私は、彼らに身の回りに目を向け、日常生活がどのように世界と結び付いているのかを自覚してもらうことから始めています。家の中にある輸入品は?街にはどの国から来た人が住んでいる?などの問いが第一歩です。
大人ができるのは環境づくり
「多種多様な人との出会い」「身近な『世界とのつながり』探し」の2種類の体験が、当事者性やコミュニケーション力を伸ばすことにつながるという話をしました。私たち大人ができるのは、そういった体験の場を設けること、つまり子どもの気付きを引き出す環境を整えたり、きっかけを与えたりすることです。
まず大前提として、わが子に世界に目を向けてほしいなら、保護者の方が世界に興味を持つことが大事です。興味のないことを人に勧めるのは難しいですし、何より保護者自身が面白がる姿勢を見せることで、子どもの好奇心を刺激できることがあります。
日々どのように世界と関わっているのか、興味深いトピックはあるか。保護者の方も考えながら、以下のような体験を家庭で実践してみましょう。
アイデア1.日頃食べている食事の元をたどる

取り掛かりやすいのは「食」をテーマにした体験ではないでしょうか。今日食べた料理の原材料がどこで生産されたものかを調べて、話し合ってみる。例えば日本の米の自給率はほぼ100%ですが、みそなどに使われる大豆の自給率は1割未満で、約9割をアメリカやブラジルから輸入しているんですよ。海外とのつながりを感じやすいと思います。
アイデア2.外国人オーナーの飲食店で食事する

「食」でもう一つ。近所に外国人が切り盛りされている飲食店があれば、足を運んでみるのも良いです。私も休日は街でさまざまな外国の料理を食べ、国巡りを楽しんでいます。食材や味付けから異文化を感じられますし、オーナーや従業員の方にその国の習慣や言葉を教えてもらえることもあります。多文化社会に生きていることも実感できるかもしれませんね。
アイデア3.地域の外国人が集まるイベントに行く

地域のイベントや、留学生のいる高校・大学の学園祭も世界を感じるチャンス。屋台やキッチンカーで知らない国の料理が提供されていたり、各国のダンス、パフォーマンスが行われていたりします。今年の筑坂の文化祭は他大学の先生に協力いただき、近隣に住むフィリピン、ブラジル、セネガルなどの方によるグルメ屋台を設けました。
アイデア4.海外の暮らし、文化、風土を体感する

高校を卒業するまでに一度外の世界に出ておくと、大学生になってから海外に行くことに抵抗がなくなります。行けるのであれば、海外研修や留学に参加してみてください。期間も行き先もさまざまな選択肢があります。欧米を選ぶ方が多いと思いますが、私としてはアジアの国々にも目を向けてもらいたいです。
★春休みや夏休みに1週間から行ける「短期留学」は、初めての海外という中高生におすすめ!
留学ジャーナルが提供している中学生・高校生向けの短期留学コース。グループツアー(春期・夏期)と、単身参加の個人留学のコースがある。
>>中高生向けの短期留学コース一覧はこちら
イマドキ学校のグローバル教育
建元さんが教員として勤務する筑波大学附属坂戸高等学校では、どのような取り組みをしているのかを教えいただきました。
1.日本と世界とのつながりを身近に

生徒たちに世界と関わり合って生きていると実感してもらうため、1年次に「グローバルライフ」という必修科目を設けています。学校の農場を歩き、見つけた植物の生産国を調べ、世界地図でその国に色を塗ったり。ポテトチップスや洗剤などに含まれるパーム油に注目して、その生産環境について学んだり。学校がさまざまな気付きの機会を早い段階で提供できれば、生徒は内向きにならず国内外に視点を向け、将来を切り開けると感じています。
2.問いを立てて、答えを追求する
2年次になると探究学習プログラム「T-GAP」がスタート。日常生活の中から生徒自ら課題を見つけ、チームを組んでアクションプランを作成し、実行します。グローバル教育の一環として行うプログラムではないのですが、外国人住民との共生や難民問題をテーマにするチームもいて、グローバルライフで身に付いた力が生かされていると感じます。
3.海外からの生徒と共に生活する

姉妹校・国際連携校があるインドネシア、フィリピン、タイをはじめとする海外から外国人留学生を受け入れています。彼らがいてくれると、海外にそこまで関心のなかった生徒たちもそれぞれの国の文化に興味を持つように。選択科目でインドネシア語を取り、いつの間にか留学生とインドネシア語で話す生徒もいますし、大学生になってから国を越えて交流を続けている子もいるようです。
4.アジアの国々の教育実習生とも交流
インドネシア、フィリピン、タイの3大学から教育実習生を迎える「SEA-Teacher」プログラムは他校にない珍しい取り組みではないでしょうか。約1ヵ月間、実習生は主に英語で授業を行ったり、ホームルームで自国の学校の様子などを紹介したりします。一生懸命コミュニケーションを取ろうとする実習生の姿を見て、生徒たちからも歩み寄る姿が見られます。
5.世界を自分の目で見て、体で感じる

筑波大学の学生と共同で国際フィールドワーク(希望制)を実施。去年と今年はAPPという製紙メーカーの工場や植林地など、普段使っている紙が生まれる現場を生で見てもらいました。他に海外姉妹校などへの1年間の留学プログラムもあり、今インドネシアに1名が留学中です。SEA-Teacherの存在やフィールドワークが留学を考えるきっかけになったようです。
筑波大学附属坂戸高等学校
筑波大学附属校の1校。通称「筑坂(つくさか)」。幅広い選択科目の中から生徒自ら科目を選択できる「総合学科」を設置し、「グローバルに考え、ローカルに実践する」一次体験を重視したグローバル教育を行う。2014年より5年間、スーパーグローバルハイスクール (SGH) に指定。2017年、国際バカロレア・ディプロマ・プログラム認定校となる。2019年よりワールド・ワイド・ラーニング(WWL)コンソーシアム構築支援事業の拠点校。
長い目で見守ることも大切
子どもに世界に興味を持ってもらう体験やきっかけを与えたら、あとは長い目で見守ってみましょう。その後の行動は人それぞれです。
筑坂の生徒でも、在学中から積極的で国際フィールドワークに参加したり2回の留学をしたりする子もいれば、高校卒業後に花開く子もいます。先日、在学中に引っ込み思案で口数の少なかった生徒が、進学先で外国人の方と英語ですらすら会話している姿を見て、とても驚きました。
条件がそろうなら、ぜひ海外留学なども検討を。私は35歳の時に青年海外協力隊としてインドネシアを訪れました。現地で視野が広がりましたし、今に続くネットワークを築くこともできました。大人になってからの海外経験でもこれだけ有意義なのですから、小中高時代の海外経験は本当にその後の人生を変えるものになり得ます。
雑誌『留学ジャーナル 2025年2月号』は小中高生の留学
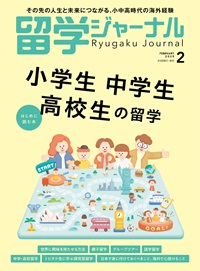
『留学ジャーナル 2025年2月号』は、留学する本人と保護者、両方の役に立つスタートブック。中高生向けの留学を徹底解説!年齢や希望別のおすすめ留学スタイルや国ごとの中学・高校の特徴など、留学をする上で押さえておきたいポイントをまとめて紹介しています。
雑誌の立ち読みはコチラ。
中学生・高校生の留学は、留学のプロにご相談を
中学・高校時代に行く短期留学や高校留学を考えているなら、50年以上の実績がある留学ジャーナルの無料の留学相談をぜひご活用ください。留学のプロが、将来の進路を見据えての計画、出発までの入念な準備、そして留学してから卒業まで、留学生の皆さんが安全な留学を送りながら、かけがえのない経験を通して将来の可能性を広げられるように、留学ジャーナルでは万全の体制でサポートしています。